平成28年度 教育プログラムの活動報告
2017/1/25 1月実習講座

1月実習講座
第4回 研究活動の把握能力の養成
平成29年1月25日(金)
宇都宮大学 陽東キャンパス OPT棟 4F コラボ室
今月は、宇都宮大学 陽東キャンパス オプト棟 4F コラボ室にて、第4回研究活動の把握能力の養成の実習講座を開催しました。午前は年に1回実施する論文理解度テストを行いました。午後からは通常の研究活動の把握能力の実習を行い、学外の研究者インタビューの内容について報告がありました。参加者は指導教員の研究支援人材育成コンソーシアム室長、茨城大学3名、宇都宮大学3名、群馬大学4名、宇都宮大学の評価委員会1名、そして事務局の2名も含め、計14名が参加しました。
 |
 |
|
| 1月 水仙 No1 | 宇都宮大学 陽東キャンパス OPT棟 |
| 1月実習講座のスケジュール | |
|---|---|
| 1. 論文理解度テスト 説明 テスト |
10:00~10:05 10:05~12:05 |
| 昼食 | |
| 2. 連絡事項 3. 研究者インタビュー報告(1) 休憩(10分) 4. 研究者インタビュー報告(2) 休憩(10分) 5. 研究者インタビュー報告(3) |
13:00~13:10 13:10~14:10 10分/ 5分×4人 14:20~15:05 10分/ 5分×3人 15:15~16:00 10分/ 5分×3人 |

1月 氷柱 (つらら) No1

論文理解度テスト 試験の様子
論文理解度テストは、一定時間内(2時間以内)に用意した論文の中から、自身の専門分野の論文と専門以外の分野の論文2通を読んで、研究内容の概要をまとめる記述式の試験になります。今年から規定用紙による自筆での提出以外に、PCによるWord形式での提出も可能にしました。
評価は、論文を提供していただいた教員により採点され、「研究内容を完全に理解出来ていると判断される。(8点)」以上を合格とし、1通あたり10点満点、合計2通あわせて20点満点で採点されます。
<評価基準> 1通ごとの採点の目安を以下に示す。
・研究内容を全く理解していない。(0点)
・レポートの一部に研究内容の理解が認められる。(3点)
・研究内容を概略理解できていると判断される。(6点)
・研究内容を完全に理解出来ていると判断される。(8点)
・研究内容を完全に理解し、その成果の特色や強みまで読み取っている。(10点)
<論文の選択>
今年は以下の分野の教員から論文をご提供いただきました。この中から専門分野と専門以外の分野の2通を選択します。
・医学 群馬大学 土橋邦生教授
・農学 茨城大学 鈴木義人教授
・理学 茨城大学 折山 剛教授
・工学1 群馬大学 石間経章教授
・工学2 宇都宮大学 鈴木 昇教授
・人文社会 宇都宮大学 鈴木富之講師
<評価結果>
評価結果については、平成29年 3月 23日 通知しました。

1月 水仙 No2
第4回研究活動の把握能力の実習は、事前に学外の研究者インタビューを実施し、研究の内容、強みと特色、産学連携や異分野間の連携の可能性について報告書にまとめます。実習当日は、インタビューした研究者2名もしくは1名の研究内容について発表がありました。
宇都宮大学 三柴URAの発表
群馬大学 保健学研究科 1名、教育学部 1名の研究者インタビューを実施
 |
 |
群馬大学 飯塚URAの発表
宇都宮大学 バイオサイエンス教育研究センター 1名、応用科学科 1名の研究者インタビューを実施
 |
 |
群馬大学 宇野URAの発表
宇都宮大学 農学部 2名 の研究者インタビューを実施
 |
 |
茨城大学 梶野URAの発表
宇都宮大学、地域デザイン科 1名、工学研究科 1名 の研究者インタビューを実施
 |
 |

1月 水仙 No3
宇都宮大学 木村URAの発表
茨城大学 理学部 1名、地球変動応用科学研究機構 1名の研究者インタビューを実施
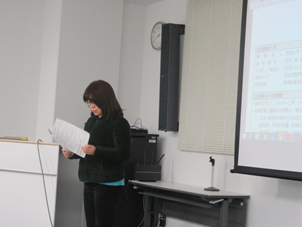 |
 |
宇都宮大学 倉山URAの発表
群馬大学 理工学府 環境創生部門 2名の研究者インタビューを実施
 |
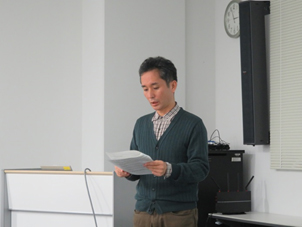 |
茨城大学 澤田URAの発表
宇都宮大学 地域連携教育研究センター 1名、教育学部 1名の研究者インタビューを実施
 |
 |

1月 氷柱 No2
群馬大学 早川URAの発表
宇都宮大学 農学研究科 2名の研究者インタビューを実施
 |
 |
茨城大学 平山URAの発表
宇都宮大学 教育学部 1名、地域デザイン科 1名の研究者インタビューを実施
 |
 |
群馬大学 布川URAの発表
茨城大学 工学部 2名の研究者インタビューを実施
 |
 |
また、研究活動の把握能力の実習は、単なる実習の教育だけで終わるものではなく、その延長線上には産学連携や異分野連携の可能性も含んでいます。実際に、この研究者インタビューをきっかけに共同研究へと結びつく事例もありました。この実習が、教育から実務への発展の可能性があることは、大学機関として効率的で魅力的な実習であると言えます。
来年度も、研究活動の把握能力の実習を継続していきます。

1月 氷柱 No3

